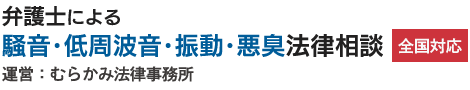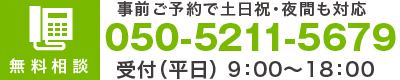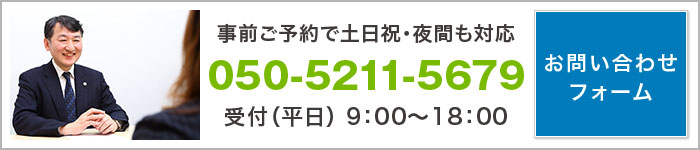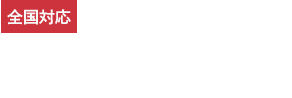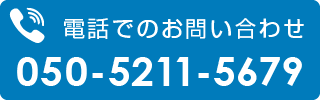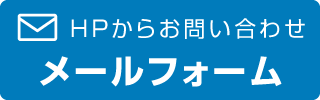公害紛争処理法の一部改正…都道府県レベルの公害紛争処理制度についてで述べた通り、都道府県レベルの公害紛争処理機関には、公害審査会方式と公害審査委員候補者名簿方式とがあり、どちらの方式を採用するかは各都道府県が決めます。
東京都では公害審査会方式がとられていますが、私は2019年4月より、東京都公害審査会の委員を務めています。任期は2022年3月までです。
東京都公害審査会委員の任務は、1)現実の事件について調停委員として関与すること(制度上は、調停のほかにあっせんと仲裁もありますが、実際に利用されるのはほとんど調停です)と、2)年2回開催される総会に出席することです(総会の定例会が年2回開催されることは、東京都公害審査会運営要綱1条2項により定められています。また、総会の開催については東京都環境局の公式ウェブサイトで公表されます)。
このうち、1)は、公害審査委員候補者名簿方式をとる都道府県においても同じはずです(候補者名簿の本来の目的ですので)。
他方、2)は、常設の公害審査会が設置されているからこそ、その総会というものが存在するわけですので、公害審査委員候補者名簿方式をとる都道府県では行われていないと思います(やろうと思えば、「公害審査委員候補者連絡会議」というようなものを開催することは可能でしょうが、それでは、公害審査会を設置するのと変わらないことになり、公害審査委員候補者名簿方式をとる意味がなくなってしまうでしょう)。
総会では、東京都公害審査会に現に係属している事件について、担当の調停委員から説明がされ、委員の間で質疑応答や意見交換がされます。このような形で情報共有をすることは、自分が個別の事件において調停委員を担当する際に大いに役立ちますので、非常に有意義であると感じています。
この点からは、公害審査委員候補者名簿方式よりは公害審査会方式のほうが優れていると言えると思います。

近隣の騒音・低周波音・振動・悪臭トラブルでお悩みではありませんか?これらの問題は、法律だけでなく音や臭いに関する専門知識が不可欠な特殊分野です。
「むらかみ法律事務所」は、この分野を最も得意とする弁護士が直接対応いたします。
弁護士歴20年近く、関連著書の執筆や弁護士向け研修の講師実績も豊富な専門家が、あなたの悩みに寄り添います。
当事務所の強みは、弁護士自らが専門機材で騒音・振動等の測定を行い、客観的な証拠確保をサポートできる点です。
また、紛争後も続くご近所関係に配慮し、「対決」ではなく「話し合い」による円満解決を第一に目指します。
ご相談は日本全国どこからでも可能です。初回のご相談は30分無料、Zoom等によるオンラインにも対応しております。
被害を受けている方も、苦情を申し立てられている方も、一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。
秘密厳守で承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。
騒音・低周波音・振動・悪臭の法律相談なら全国対応の「むらかみ法律事務所」