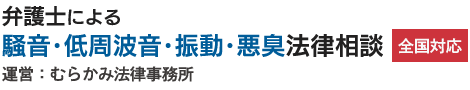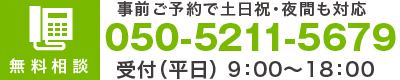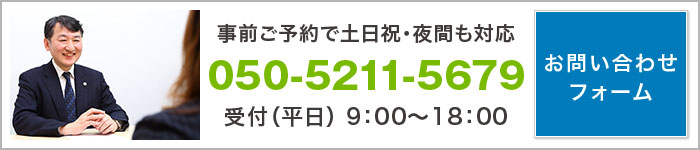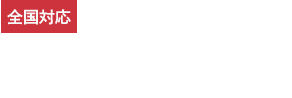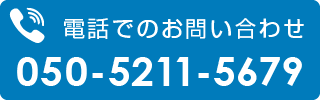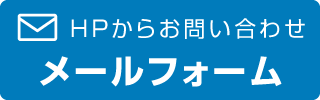JIS Z 8731(環境騒音の表示・測定方法)は、騒音の測定方法について定めた日本産業規格で、騒音を規制する法律や条例では、ほとんどの場合、騒音の測定方法はJIS Z 8731によると定められています。
このJIS Z 8731は、1999年に定められたものが長く用いられてきましたが(JIS Z 8731:1999と表記されます。その一世代前は、1983年に定められたJIS Z 8731:1983でした)、2019年に改正され、現在通用しているものはJIS Z 8731:2019です。
JIS Z 8731:1999とJIS Z 8731:2019を比較すると、かなり重要な変更点があります。これから、それらを数回にわたって御紹介します。今回は「騒音」の定義についてです。
JIS Z 8731:2019では、「1 適用範囲」のところに、「・・・環境騒音とは、一般の居住環境における騒音(望ましくない音)をいう」という文章があります。このような「環境騒音」や「騒音」の説明は、JIS Z 8731:1999にはありませんでした。
JIS Z 8731:2019の上記の文章は、「環境騒音」及び「騒音」の定義を示したものとみてよいと思います。
「騒音」の定義は法令にはなく、その代わりに公的権威のある騒音の定義として、JIS Z 8106(音響用語)には、「不快な又は望ましくない音、その他の妨害。」という定義が載っています。私はこの定義を「騒音・低周波音・振動の紛争解決ガイドブック」で引用しました(57頁)。
けれども、私は、この定義の「その他の妨害」というところが余分だと思い、あまり適切な定義だとは思っていませんでした。この表現だと、音以外のもの(「妨害」)が「騒音」となりうるように読めますが、それは一般常識からかけ離れ過ぎているでしょう。
今回、JIS Z 8731:2019に、騒音とは望ましくない音のことであるという意味の表現が入りましたので、これからは、「JIS Z 8731:2019によれば、騒音とは望ましくない音のことである」と説明すればよいと思います。「望ましくない音」というのは、シンプルでよい定義だと思います。

近隣の騒音・低周波音・振動・悪臭トラブルでお悩みではありませんか?これらの問題は、法律だけでなく音や臭いに関する専門知識が不可欠な特殊分野です。
「むらかみ法律事務所」は、この分野を最も得意とする弁護士が直接対応いたします。
弁護士歴20年近く、関連著書の執筆や弁護士向け研修の講師実績も豊富な専門家が、あなたの悩みに寄り添います。
当事務所の強みは、弁護士自らが専門機材で騒音・振動等の測定を行い、客観的な証拠確保をサポートできる点です。
また、紛争後も続くご近所関係に配慮し、「対決」ではなく「話し合い」による円満解決を第一に目指します。
ご相談は日本全国どこからでも可能です。初回のご相談は30分無料、Zoom等によるオンラインにも対応しております。
被害を受けている方も、苦情を申し立てられている方も、一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。
秘密厳守で承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。
騒音・低周波音・振動・悪臭の法律相談なら全国対応の「むらかみ法律事務所」