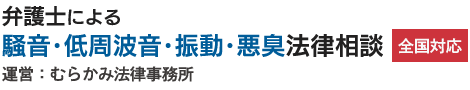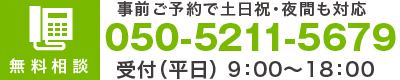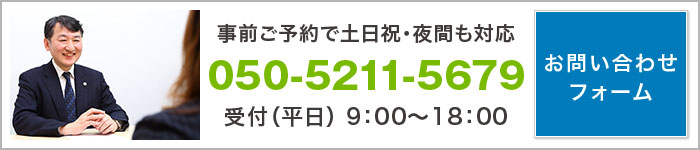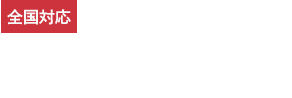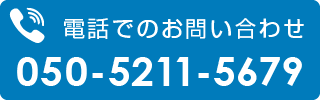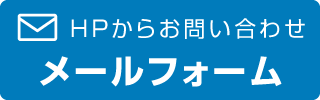※本稿が念頭に置いているのは、低周波音の身体的影響です。
低周波音に関する最も権威のある指標は、2004年に公表された環境省の参照値(「低周波音問題対応の手引書」に記載されています)ですが、エネファームやエコウィルに関する消費者庁の報告書(2017年)では、感覚閾値(聴覚閾値)が重視されています。
消費者庁は、環境省の見解とは異なり、「低周波音の人に対する影響の指標としては、参照値よりも、(参照値より低いレベルである)感覚閾値のほうが重要であり、低周波音の測定値が感覚閾値以上であれば、低周波音の人に対する影響が生じうる」という考えです。ただ、環境省も、参照値よりも低いレベルの低周波音であっても、人に対する影響が生じうることは認めています。
感覚閾値は、国際規格であるISO 389-7によって定められているのですが、不思議なことに、消費者庁の報告書には、感覚閾値の具体的な数値は記載されていません。
一方、私の著書である「騒音・低周波音・振動の紛争解決ガイドブック」の226ページには、ISO 389-7による感覚閾値の数値を書きましたが、これは中野有朋氏の『あの音が私を苦しめる!? 低周波音・超低周波音トラブル解決法』の47ページに記載されていたもので、そこには20ヘルツから80ヘルツまでのバンドについての感覚閾値のみが記載されていました。
しかし、前記の消費者庁の報告書では、100ヘルツ及び125ヘルツの音(これは「低周波音」の領域を外れますので、「音」と書きます)によっても、人に対する身体的影響が生じうるということが述べられています。
以上の次第で、100ヘルツ及び125ヘルツの音のISO 389-7による感覚閾値の数値が知りたいと思ったのですが、インターネットで検索してみても、ISO 389-7による感覚閾値を各バンドごとの正確な数値で示した文献はヒットしません(感覚閾値のグラフは見つかるのですが、グラフでは正確な数値がわかりません)。
そこで、国会図書館のデータベースで検索してみると、さすがは国会図書館で、ISO 389-7そのものが所蔵されていることがわかりました。ただし、東京本館ではなく関西館に所蔵されているため、東京本館で見たい場合にはインターネットで申し込んで取り寄せてもらう必要があります。取り寄せには数日かかります。
先日、そのようにして取り寄せてもらったISO 389-7を東京本館で閲覧してきました。本来はもっと早くに見るべきものでしたが、初めて見たISO 389-7は、10ページ程度の薄い英語の冊子でした。そして、感覚閾値の具体的な数値が、20ヘルツ~18,000ヘルツの各バンド(1/3 オクターブ)について、小数点以下第1位までの数値で書いてありましたので、知りたかったことを知ることができました。
上記の中野有朋氏の著書では、感覚閾値は整数で示されていたのですが、もともとのISO 389-7では、感覚閾値は小数点以下第1位までの小数です。中野氏がなぜ著書の中で整数に丸めた数値を書いたのかは不明です。
また、私はこれまで、多くの文献にならって「感覚閾値」と呼んできたのですが、英語の表現は”threshold of hearing”ですので,「聴覚閾値」のほうが訳語としては正確です。消費者庁は「聴覚閾値」という表現を使っています。
125ヘルツ以下のバンドについての感覚閾値の具体的な数値は、ISO389-7による音の感覚閾値(聴覚閾値)のページをご覧下さい。

近隣の騒音・低周波音・振動・悪臭トラブルでお悩みではありませんか?これらの問題は、法律だけでなく音や臭いに関する専門知識が不可欠な特殊分野です。
「むらかみ法律事務所」は、この分野を最も得意とする弁護士が直接対応いたします。
弁護士歴20年近く、関連著書の執筆や弁護士向け研修の講師実績も豊富な専門家が、あなたの悩みに寄り添います。
当事務所の強みは、弁護士自らが専門機材で騒音・振動等の測定を行い、客観的な証拠確保をサポートできる点です。
また、紛争後も続くご近所関係に配慮し、「対決」ではなく「話し合い」による円満解決を第一に目指します。
ご相談は日本全国どこからでも可能です。初回のご相談は30分無料、Zoom等によるオンラインにも対応しております。
被害を受けている方も、苦情を申し立てられている方も、一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。
秘密厳守で承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。
騒音・低周波音・振動・悪臭の法律相談なら全国対応の「むらかみ法律事務所」